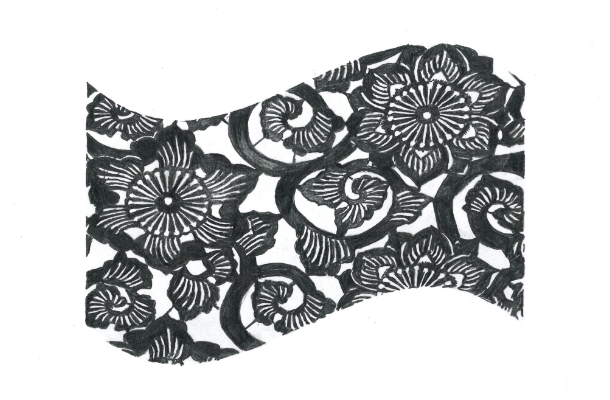菌の物語
 第9巻
第9巻- 第2話「藍」に宿る微生物 -発酵を利用した染色の神秘-
明治時代に初めて日本を訪れた小泉八雲の心も捉えたという、天然の藍で染めた「藍染」は、発酵の力を用いた染色であることをご存じですか?現在では工業的に染色されたものがほとんどですが、もともとはタデ科の「アイ」という植物を使った染色でした。
藍染めに利用できるアイにはいくつか種類がありますが、中でも「タデアイ」という種類の植物がよく利用されます。このタデアイをそのまま利用するのでなく、発酵させて「すくも」という染色材料に加工してから染めるのが、いわゆる伝統的な藍染めとよばれるものです。
タデアイは5月に種を蒔き、7月から8月にかけて収穫し、細かく裁断して一旦乾燥させます。そして、これを発酵させ「すくも」に加工するのですが、すくも作りは高温(70度程度)の中で、発生するアンモニアの刺激臭に耐えながら、3か月という長期間にわたって作業を行うという過酷なものです。
こうして出来上がったすくもを、他の材料と混ぜてさらに発酵させ、実際の染料を作っていくのですが、この手法は「天然藍発酵建」と呼ばれます。すくもと、木灰から取った灰汁(あく)、石灰を混ぜ、そこに微生物のエサとなるふすまや清酒などを入れ、30度前後で1~2週間発酵させることで染料が出来上がるのです。藍染めの青の成分「インディゴ」はすくもの中には水に溶けない形で存在しているため、そのままだと色が付きません。発酵の作用で不溶性のインディゴは水溶性に変わり、染料として利用することが出来るようになるのです。
藍には、防虫効果、防カビ効果、消臭効果などの効果に加え、生地を強くする効果もあります。さらに、藍の服を身につけると傷を負っても化膿しにくいことから、武士に重宝されていたともいわれています。日本の伝統文化である藍染は、発酵の過程で様々な成分が絶妙な深みを生み出し、化学的な「合成藍」には決して真似できない独特の美しさを加味してくれるのです。そして、それは暮らしの知恵に根ざした伝統技術でもあったのです。